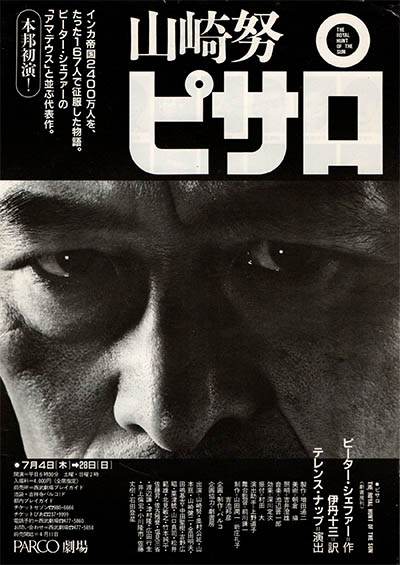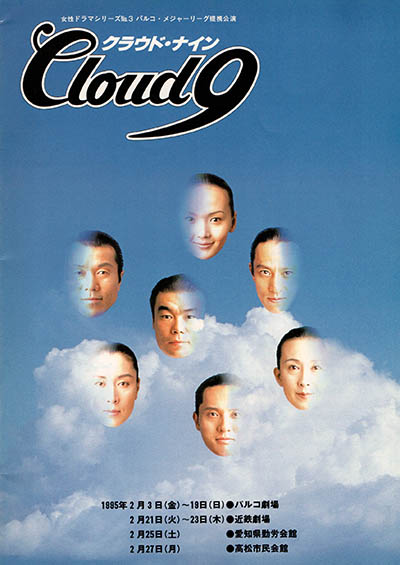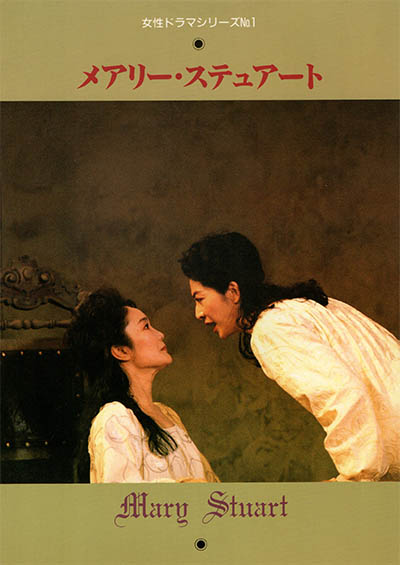- 笹部 博司 Official Site
-
- 脚本
- 演出
- プロデューサー
これまでのこと これからのこと
大学時代は、ほとんどアルバイトをしていた。紛争で大学は封鎖、レポート提出で単位を獲得し、かろうじて卒業した。東京へ出た。定職に就かず、またアルバイト。ない日は、夜明けに寝て、昼過ぎに起きだし、喫茶店で漫画を読んで、夕方まで時間をつぶし、朝までテレビを見る。そんな生活を5年近く続けた。何もなかった。ただ時間だけがあった。今でもあの空白の時間に戻りたいと思うことがある。
それから、本は嫌いじゃないからと書店に就職した。書店員をやりながら、突然、出版社を始める。芝居がやりたかった。でも、場所を見つけることが出来なかった。ぼくにとっての芝居は、演劇書の出版だった。
つくった出版社の名前が劇書房、そこで世界のベストプレイを出版し、その上演を企画する。そういう風にぼくの演劇活動は始まった。
江守徹による五万語のモノローグ「審判」(その後、加藤健一で上演、翻訳青井陽治)、1980年を皮切りに、矢崎滋・角野卓造「ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ」(その後、生瀬勝久・古田新太で上演、翻訳松岡和子)、山崎努・渡辺謙「ピサロ」、大竹しのぶ「奇跡の人」、三國連太郎・加藤健一「ドレッサー」(柄本明で再演)、木野花演出で評判となった「クラウド9」(翻訳伊丹十三)、西城秀樹・市村正親・鳳蘭の三人のミュージカル「ラヴ」などなど。
1990年に演劇製作会社メジャーリーグを立ち上げ、その第1回目の舞台「メアリー・スチュアート」を上演した。演出宮本亜門、出演麻実れい・白石加代子。これを機に、演劇の企画の中心は白石加代子となる。白石加代子・高畑淳子・片桐はいり「女たちの十二夜」、白石加代子・范文雀・緑魔子・松金よね子「トップガールズ」、そして1992年岩波ホールで、「百物語」がスタートする。
その次の作品が、蜷川演出の「身毒丸」である。人生の中ではありえないことが起こるものだ。それがその当時トップアイドルだった武田真治の出演である。正直、読んで面白い本ではない。制作発表の時、武田真治は「読んで一行もわからなかった」と公然と言い放った。マネージャーが俳優に相談なくこの企画を決めていたのだ。松浦さん、そのマネージャーの名だ。彼がいなければ、「身毒丸」という奇跡は、存在しなかった。なぜ、彼は、武田真治を「身毒丸」に出演させたのだろう。
因みに、その制作発表に同席した宮川彬良は「彼の答えは正に初めて台本を手にした時の私の感想を代弁していた。その態度は堂々として、いい男っぷりだった」と、語っている。
「身毒丸」が蜷川幸雄との出会いとなった。この企画の話をした時、蜷川さんは言った。
「寺山の説教節、白石加代子が継母で、武田真治が義理の息子、それを俺が演出する。小劇場演劇の総決算をしながら、これからの演劇の扉をひらくわけか」
口が滑った。
「蜷川さんの芝居って、最初の5分、息を呑むじゃないですか、それが90分続くんです」
無視された。
天才蜷川幸雄を堪能できた幸せな稽古場だった。
撫子としんとくが出会った親子の道行の場面ができた時、思わず涙が出た。
稽古場であれやこれや言って嫌がられていた。
「今日の稽古を見て、安心したからもう来ない」
涙目のぼくを見て、蜷川さんは言った。
「そんなこと言わないで、来いよ」
実際に稽古場には数日足を運ばなかった。
久しぶりに行くと、息を呑むようなすごい場面が次々と出来上がっていた。
「高校生はこんな言葉をしゃべりません」と、武田真治は稽古場には来ているが、稽古には参加しない。
蜷川さんはそれには構わず、どんどん場面を作っていく。
そして、最後に、その作った世界に武田真治を立たせて、悪夢の世界に引きずり込んだ。
圧巻の地獄めぐり。
大阪での公演が終わった後、興奮冷めやらぬ様子でしゃべるこんな声が聞こえた。
「うち、このまま、家に帰って、布団をかぶって寝てしまいたい」
こんなうれしい評はなかった。
「素敵な悪夢をみせてあげる」、これが「身毒丸」のキャッチコピーだった。
再演でのしんとくは、オーディションで選ばれた藤原竜也。藤原竜也を得て、舞台はより過熱し、爆発的なヒットとなった。白石加代子の撫子、藤原竜也のしんとく、あれほど、観客を熱狂させた舞台を知らない。
寺山修司の「奴婢訓」を晴海で観た。驚くべき舞台だった。それがきっかけで、寺山修司の戯曲全集を企画した。寺山修司の書いた戯曲はすべて目を通した。そして、「身毒丸」を自分の手で上演したいと思った。初演のパンフレットにこう書いた。
「『身毒丸』が日本の演劇の中で重要だと思うのは、この作品の中で音楽が果たしている役割の見事さである。そして日本的な題材を使いながら、音楽劇というエンターテインメントを成立させるこんな手があったのかという発見である」
「身毒丸」の共同執筆者の岸田理生に全面的な書き直しを頼んだ。書き直しのポイントは、しんとくと撫子は出会った瞬間、運命の一目惚れをしたという点だ。理生さんは、見事なメロドラマに書き換えた。客席で「身毒丸」の芝居を観ていて、放火魔の気分だった。「俺が火をつけたんだ」。そしてまた、夢をみているようだった。その時、忽然と現れ、忽然と去って行った松浦さんのことが思い浮かんだ。ホントの意味で火を点けたのは彼だ。彼がいなかったら、この舞台は存在しなかった。

明治座で「身毒丸」のパンフレットの打ち合わせをしているときである。蜷川さんは、突然、こう切り出した。
「笹部、俺、シアターコクーンの芸術監督になるんだ」
10年以上も、抱えていた作品がふっとひらめいた。
「この際、どさくさに紛れて、やりたい芝居があるんですけど」
「なんだ」
「『グリークス』、ギリシャ人という意味です。人間という意味でもあると思う。ギリシャ劇10本を、一つの芝居にした、まさに人間が凝縮された、上演時間は9時間の芝居。お客は一瞬も飽きることなく見続ける。あっという間の9時間ドラマです」
イメージキャストを言った。
蜷川さんはにやりと笑って言った。
「化け物を集めて、俺に演出させるんだ」
蜷川さんの「夏の夜の夢」(ポイント東京製作)は傑作舞台だ。その稽古場で、タイテーニアを演じる白石さんにこんなダメだしをした。
「タイテーニアは妖精の女王なんだ。加代ちゃんのタイテーニアは妖精というより妖怪なんだけど」
白石さんは帰りの車の中でぶすりと言った。
「蜷川さんのタイテーニアは土の中から出てくるんだ。土の中から出てくるんだから、妖精なもんか、妖怪じゃないか」
白石加代子のタイテーニアが、ロンドンでも絶賛された。ベニサン・ピットで上演されたこの舞台が、蜷川幸雄を復活させた。「身毒丸」の演出も、その舞台を観て、決意した。
「グリークス」の出演交渉で平幹二朗に会った。
平さんは言った。
「クリュタイムネストラはどなたがおやりに?」
「白石さんです」
「ふうん。で、アンドロマケは?」
「麻実さんです」
「そうですか。で、ぼくは?」
「アガメムノンです」
「笹部さん、ギリシャ劇は女の役が面白いんです。男の役はね・・・」
一旦は断られた。平さんなくして、あの舞台は成立しなかった。
「グリークス」はその年のこの一本という舞台になった。
蜷川さんとの最後の舞台は、「ペリクリーズ」だ。
三味線を弾きながら放浪する夫婦に市村正親と白石加代子を起用し、二人の語りで舞台を進行させるというのが出発点だ。企画はしたが、稽古場には一度も足を運ばなかった。ビデオで見直してあまりの面白さに驚いた。
蜷川さんには何でも言った。調子に乗って、嫌がられて、そのうち遊んでもらえなくなった。

それから14年後、高畑充希と白石加代子で「エレクトラ」をやった。もっと人間がやりたかった。では人間とは? ぼくは、人間はイプセンで体験した。人間とは不可解で矛盾に満ちた生き物、グロテスクで欺瞞に満ちている。そして何があってもしたたかにしぶとく生き延びる。イプセンは、近代という時代の中でギリシャ劇をやりたかった。ぼくは、もっと人間臭いギリシャ劇に挑みたかった。あえて言えば、笑いを持ち込みたかった。人間のあまりの愚かさに、馬鹿馬鹿しさに、思わず笑ってしまう、そんな悲劇・・・
芝居を企画する、それが生きがいだった。
蜷川さんは、常に言っていた。
「笹部、プロデューサーがクリエイターになろうとしてはいけない。プロデューサーが演出や、脚本を書くことに手を出すべきではない。そこに手を染めると、プロデューサーは役者に信頼されなくなる」
その通りだと思った。自分が脚本を書いたり、演出ができるとは思えなかった。
自分ができないことをできる人を集めて、芝居を作る。その役を誰でみたいか、それを誰に演出させたいか、すべて人に託す、それがプロデューサーだ。
それがいつ変わり始めたのか、はっきりと自覚できるのが、「野鴨」との出会いである。50半ばの頃である。本箱にイプセンの「野鴨」があった。自分が買った本ではない。イプセンは、自分の興味の外にある作家だった。ふと手に取って読んだ。正直、よくわからない。この作品は一体、何だ?と思った。何度も繰り返し読んだ。隠された秘密が、少しずつ見えてきた。とてもエキサイティングだ。その発見を自分なりの文章にしていった。それはとてつもなく楽しい作業だった。見えてくるのは、人間である。寒い時、人間はたくさんの服を着こまないと、凍え死ぬ。その服を欺瞞という言葉に置き換える。そしてイプセンはその服を一枚、一枚はぎとっていく。快感だった。それからイプセンにのめりこんだ。イプセンの書いた作品を自分なりの考えで台本にした。イプセンは面白い、わくわくする、ドキドキする。みるに堪えないような、聞くに堪えないような、ひどい話ばかりではないか。なのに、わくわく、ドキドキなんて。言えるのは、そこにはホントがある、まぎれもないホントが。そのホントに触れると、ほっとして、慰められ、癒される。人間は嘘をつき、間違い、罪を犯す。そして生き続ける。イプセンは自分の内面を書き続けた。彼は作品を通して、自らを懺悔し、その内面が犯した罪を告白しているのだ。ぼくの無人島へ持っていきたい本は、イプセンだ。ぼくの中のイプセンは、世間一般のイプセンとまったく違っている。だって、楽しいんだもの。
人生には思ってもみないことが何度か起こる。新潟に新しい劇場ができる、そこを手伝ってくれないかという話をもらった。最初の2年間に上演するレパートリーを作った。そして、盟友宮川彬良の助けを借りて、市民参加のミュージカル「シャンポーの森で眠る」も制作した。気が付くと、劇場の芸術監督という地位を与えられ、人生の3分の1をりゅーとぴあ(劇場の名前)で過ごしている。
今、やりたいのは演劇、自分で台本を書いて、自分で演出をする。その機会をくれたのは十朱幸代さん。新潟で「物語の女たち」という女優によるリーディングの企画を立ち上げた。司馬遼太郎原作の「燃えよ剣」を、土方歳三の女、お雪のモノローグドラマとして作った。それを上演する際、演出をやらせてほしいと申し出たら、思いのほか、オッケーの返事をもらった。
そしてもっと奇特な人が現れた。井上芳雄さんである。女のシリーズの好評を受けて、男のシリーズを企画した。アウシュビッツを生き抜いたヴィクトール・フランクルの書いた「夜と霧」である。その上演を芳雄さんが受けてくれた。幸運なことに、芳雄さんとの仕事は「星の王子さま」「十二番目の天使」と続く。
笹部博司の演劇コレクションはこれまで12冊出版した。それ以上出すと、破産するといわれ、諦めた。その中で上演したのは、大地真央「トスカ」、仲代達矢「ジョン・ガブリエルと呼ばれた男」、雛形あきこ・渡部豪太「令嬢と召使」、勝村政信・とよた真帆「ちっちゃなエイヨルフ」、安寿ミラ「宋家の三姉妹」、とよた真帆「フェードル」、松井誠「メディア」など。
僕の嫌いな本のベスト2が「星の王子さま」と「銀河鉄道の夜」。読み始めるけれど、いつも最後までたどり着けない。どうしてこの本を人は面白いと思うのだろう。鰯の頭の信心のように、そう思い込んでいるだけだ。それとも自分が馬鹿なのか。悔しくて、意地になって取り組んだ。すると見えてきた。「野鴨」と同じだ。「大切なことは、目には見えない」その見えてきたことを、上白石萌歌に話した。彼女との出会いは幸運だ。それを彼女は見事に体現した。
深川麻衣との出会いも幸運だった。真っ白な麻衣ちゃん。彼女はそっくりとその心を預けてくれた。彼女とやった「ふじ子の恋」「英二を愛した女」「柳橋物語」は、はっきりとした成長のプロセスだった。
水石亜飛夢とやった「二十歳の暗殺者(ロレンザッチョ)」は、また挑戦してみたいと思う舞台である。あの孤独で切ない暗殺者に挑んだ亜飛夢の勇気と精神力の高さは忘れられない。
本を読んで気に入ると、芝居の台本にする。一体、そんな台本がいくつ貯まっていることだろう。
最近上演した渡辺徹・内博貴「イン・ザ・プール」は、その一つ。渡辺徹がデブの精神科医伊良部、そして内博貴がその患者。水泳にはまった二人は、夜の体育館へ忍びこむ。
「ああ、パトカーだ」という内君の声が忘れられない。
あの声で、シェイクスピアをやりたい。
りゅーとぴあではもう20年、「アプリコット」という子供の劇団をやっている。ここでの活動が、ぼくに劇作、演出の道を開いてくれた。毎夏新作を発表し、市民の人たちも楽しみにしてくれている。
最近、生まれ故郷である姫路で、高校生でのシェイクスピアを三年連続で上演した。「お気に召すまま」「マクベス」「ハムレット」、これはこれからもずっと続く予定である。
そして終わったばかりの公演が、新潟のシニアの人とやった「瞼の母」。始まる前、雑誌の取材で、プロの舞台より百倍面白いものを作ってみせると大言壮語した。出演者全員が、心の底から楽しみのめりこんだ。そこにはどこにも嘘はなく、ホントしかなかった。プロより百倍面白い舞台ができたかどうかは、わからない。でも演劇経験のないシニアの舞台を、お客は本当に笑い、泣き、楽しんでくれたのはホントだ。
60を過ぎてから演出を始めた。こんなに楽しいことはない。演出だったら、どんなところでも、どんな人たち相手でもやりたい。やりたいものは、いっぱいある。いっぱい、いっぱい、いっぱい・・・
ぼくは、演劇に関しての知識は、ほとんどシェイクスピアから得ている。
例えば、マクベスはこういう。
「心に思っただけで、心臓が高鳴り、胸を突き破りそうだ」
心に思うということは、想像するということだ。しかし、心臓の高鳴りは現実である。
心に思うと、体がかっと熱くなる。
芝居の中で俳優は、架空の世界で、架空の人間である。それは役を演じることではない。架空の世界の架空の人間はあくまでも自分である。自分の思考を使って、想像の世界を生きていく。思いがけない出来事の中で、思ってもみない自分がいることを発見する。ぼくたちも、思ってもみない現実を前にして、それまでの自分なら決して考えない思いで突き進んでいる自分を発見することがある。シェイクスピアによれば、恋をすれば、それまで考えられない馬鹿なことを次々にやっている自分を発見する。恥ずかしくて、もう絶対にこんなことをやめようと決意をしても、もっと馬鹿なことをしている自分がいる。思い通りにならない人間が暴走し始める、観客が観たいのはまさにそれだ。観たいのは人間だ、演技ではない。
シェイクスピアはまさに暴走する人間、破滅に突き進む人間を描いている。ある瞬間、知らない人間が現れ、暴走をはじめ、砕け散るまで走り続ける。破滅し、浄化が訪れる。それがギリシャ悲劇だ。
イプセンはそれを近代劇の中で成立させようとした。
先だって、岡本綺堂の「修禅寺物語」を、カノンの調べで上演した。「修禅寺物語」は死にゆく人たちの物語である。蝶が次々に火の中に飛び込んで、燃え尽きて、死んでいく。俳優は、その架空の中で、自分のイメージを燃やし尽くし、退場する。岡本綺堂の素晴らしい日本語が、その悲劇を、美的な官能的な世界へと変貌させる。登場して、退場する、それが人間の運命である。であれば、その運命の中で、与えられた命を燃やし尽くすことが人間に出来ることである。そしてそれが俳優に出来る唯一のことである。
そんな演劇を命が尽きるまでやりたいと思っている。
「あるものはなにもない。あるものはないものだけだ」
マクベスの言葉だ。
手に入れたものは、手に入れた瞬間、ないものになる。
だから、いつも心の中は、ないものだけだ。
どんなにたくさんのものを手に入れても、心の中は、いつも無・・・
死ぬ瞬間もその思いでいることが出来れば、と思う。
まだ、何も成し遂げてはいない。
これからの人生で、何かを成し遂げることが出来るのだろうか。
「あるものはなにもない。あるものはないものだけだ」
その瞬間、マクベスは破滅への道を突き進んだ。
わくわくしていたことは間違いない。
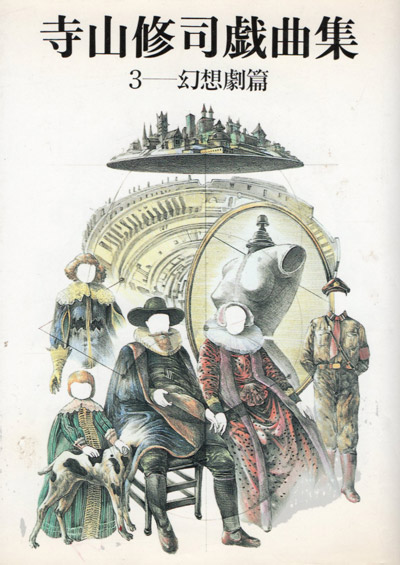
寺山修司のところへ、出版する戯曲集のあとがきを取りに行った時のことを思い出す。体の具合が悪いから1時間以内にと言われた。なのに、宝塚の「ベルばら」のビデオを持ち出して、長谷川和夫の演出を解説してくれた。宝塚の演出をしたいと語った。廊下をお母さんが何度も通り過ぎて、食事を告げる。立ち上がって帰ろうとするが、また別のビデオを取り出す。歌舞伎の演出の話もした。「電気釜の中から首が出てくるんだよ」話は終わらない。「僕はどんな本だって、例えば資本論だって、ひと月で芝居にしてみせる」
そう語る寺山修司には、いつにも増して熱気があった。昼過ぎに行って、帰る頃は暗くなっていた。
翌日寺山さんは入院し、一ヶ月後帰らぬ人となった。もらった原稿の日付が、1983年4月4日、そして亡くなったのが5月4日。
その時の寺山修司は成し遂げた人ではなかった、これから成し遂げようとしていた人だった。
シェイクスピアやイプセンも夢の中をさまよいながら、そのまま、あの世という世界にたどり着いていることを願っていたように思う。
自分のこれからを思えば、死ぬまで、演劇という夢にしがみついて生きていきたいと思っている。